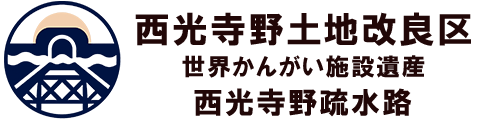灌漑(かんがい)とは、農作物を育てるために田畑へ水を供給する仕組みのことです。
特に雨の少ない季節や地域においては、自然のままでは水が足りないため、川や湖などから水を引く「灌漑施設」が必要となります。灌漑施設には、水路、ため池、堰(せき)、隧道(ずいどう=トンネル)などがあり、先人たちの工夫と努力によって築かれてきました。
現代に至るまで、これらの施設は地域の農業を支え続けており、その歴史的・技術的価値が評価され、「世界かんがい施設遺産」として登録されているものもあります。
「西光寺野(さいこうじの)」は、兵庫県姫路市郊外の自然豊かな農村地帯で、歴史ある疏水路が今も残る地域です。
この地名は、かつて近くにあった寺院「西光寺」に由来し、その周辺一帯を「西光寺野」と呼ぶようになったと伝えられています。※
江戸時代、この地で開かれた農地に水を届けるために築かれたのが、「西光寺野疏水路」です。
現在では、地域の文化財としても大切に守られ、「世界かんがい施設遺産」に登録されています。地元住民の手で維持・管理されてきたこの疏水路は、地域の誇りであり、未来へ伝えたい水の文化です。
📌 角川日本地名大辞典による説(JLogosより)
播磨地域をあつかう角川地名大辞典では、地名「西光寺野」は“法道仙人が開基した西光寺にちなむ”と記述されています。この西光寺は、嘉吉(かきつ)年間(1441〜1444年頃)まで存在し、地名の由来とされる寺院であると明記されています。さらに「西光寺野」は『風土記』の「邑日野(おほひの)」に比定されるともされています。JLogos(無料辞書サイト)
📚 郷土史や町の資料の記述
福崎町の資料には、西光寺野用水や土地の歴史に関する記録があり、地名が「西光寺村」などに由来する可能性について触れられている文書も存在します。また、姫路市・福崎町をまたぐ西光寺野台地の開発史についても明記されています。福崎町公式サイト